NICA Press® とは

- NICA
-
News & Insight from the Community of Academics - 学術共同体からのニュースと知見
-
News
日常のありふれたニュースではなく、学術関係者が自身の研究を論文や学会以外の場で気軽に「発表」「公開」「報告」できる学術報道を目指します。
-
Insight
学術的洞察。専門誌を超えた学術的裏付けや背景分析
-
Community of Academics
大学や研究機関のみにとどまらない、「知の担い手」たちのネットワーク形成を目指します
-
NICAは、これまでにない学術コミュニティ発の報道プラットフォームです。
専門的知見に基づきながらも、誰にでも分かりやすく伝えることを目的としています。学会や論文など「専門知としての世界を社会とどう接続するか?」それがNICA の使命です。
本部の承認を受けた学術関係者(現職または元アカデミックポスト保持者)が、社会的意義のある事象について、学術的な視点から情報を発信します。
国家規模のプロジェクトから地域の動向まで、規模を問わず「社会性」と「学術の公共性」という原則に基づき、信頼性の高い情報を即時に共有できる新しい報道の仕組みを構築していきます。
-
オリジナル原稿の投稿者
教員・研究者・教育(アカデミックポスト現職・退官・退任者)
-
同研究室の大学院生
噛み砕いてわかりやすく2次配信することで「教育的効果」+「発信力」を発揮
-
学部生
さらに噛み砕いて既存のSNSから生活世界へと接続
NICA Press の目的

"Academic Journalism"
酷似する膨大な報道の洪水から、知的精査に基づく「学術報道」へ、
情報過多の時代において、NICAは報道の質的転換を目指します。
専門的知見と社会的文脈に根ざした分析を通じて、学術的に裏付けられた報道のあり方を提示します。
報道の氾濫を越えて、知に基づく価値ある情報
── Academic Journalismの新地平へ
情報の洪水から、構造化された知へ
── 学術報道というスタイルを貫きます
量から質へ、速報から考察へ
── Academic Journalismというカテゴリーを開拓します
すべての記事を研究者が精査し、専門的な視点から深く掘り下げた、新しい「学術報道」の形を提案します。各分野の学者が科学的かつ学術的な基盤に基づいて分析したより高い信頼性と深みのある情報を提供します。
このプラットフォームは、学術的でありながら多角的な理解を可能にするよう配慮されています。専門的なレポートや論文を活用しつつも、一般の読者にもわかりやすい形で情報を届けることで、専門家でなくても理解できる報道(生きた社会との接続)を目指します。
つまり、「誰にでもわかる学術レポート」の実現がこの新しい報道の使命です。学者が解説委員として活動し、研究者の卵たちが専門的な知識を平易な言葉で伝えることで、一般社会言語へと翻訳する。
複雑な専門解説をシンプルで親しみやすい表現に変換する。そんな新しい学術報道の姿を追求していきます。
大学名誉教授・現職教授・高等教育教育者・研究者を中心としたメンバーで構成されるスカラーズ・ギルドの社会変革事業の一環として取り組んでいます。
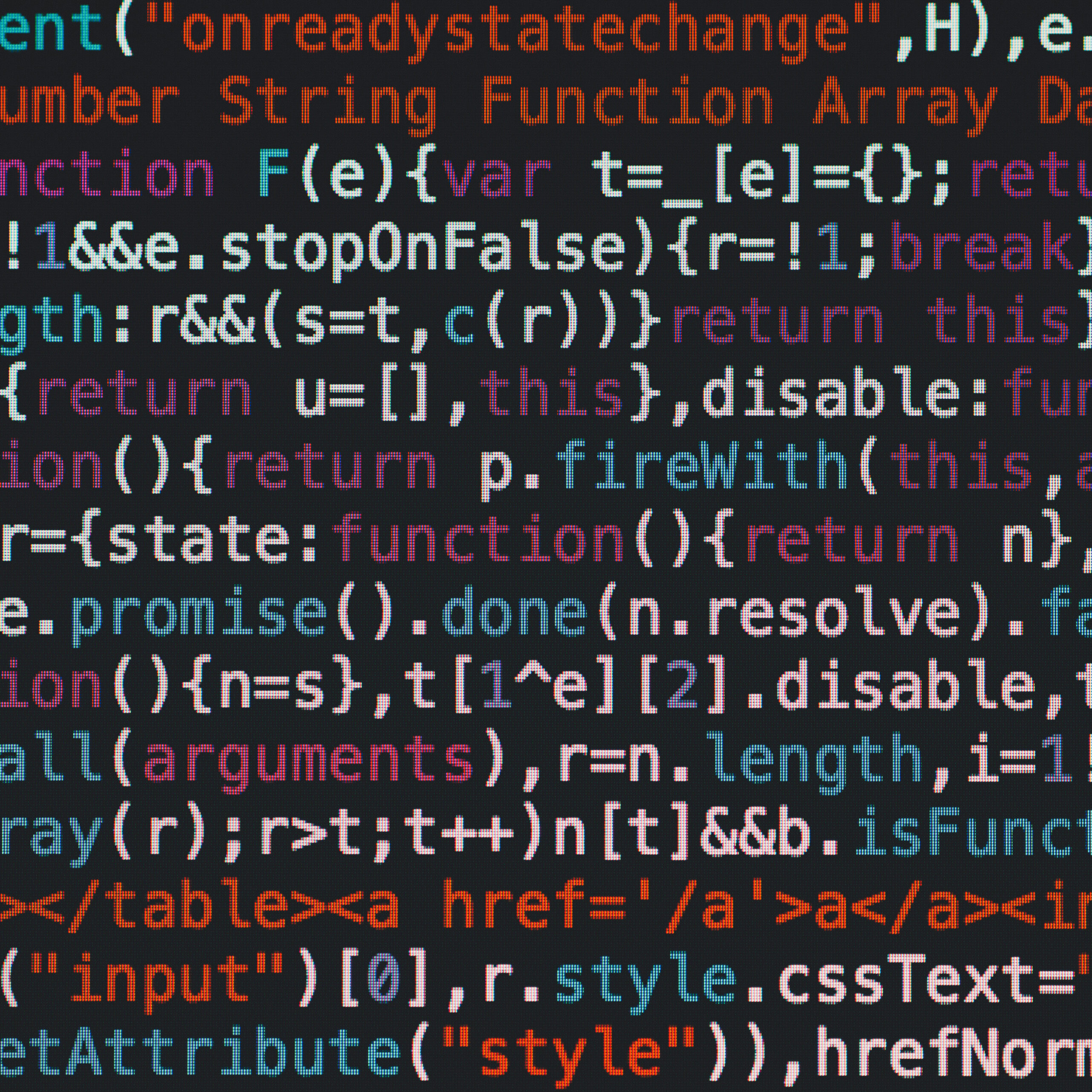




哲学

政府・政党・通信社・新聞社など、
特権的で限られた情報発信源からの解放・・・
これまでの報道はメディアのカラーによって記事として脚色されたものしか存在しなかった。
それ以外に存在するとすれば、それはフェイクニュースの類だけであった。
これまでのメディアではない、新しい公共財としての「知る価値」のある「報道知識」を共有できるようにしたかった。
世界全体の正しい理解の総量を増やしていくこと、ーーーこれがNICAPressの目的です。
SNS型報道の構造的課題
情報の即時性と公共性の乖離・・・
現代の情報環境において、SNSはもはや報道の補完的手段ではありません。いまや、それは事実上の「第一報」として機能し、個人が発信した情報が瞬時に拡散されていきます。そこには、従来の報道機関が担ってきた検証や編集のプロセスは存在せず、未整理の情報がそのまま公共空間に影響を及ぼしているのです。
この即時性は、災害や緊急事態においては確かに有用です。しかしその一方で、情報の信頼性、文脈性、そして倫理性が軽視される傾向が、静かに、しかし確実に広がっています。
SNS型報道の本質は、「共有されること」そのものが価値とみなされる構造にあります。アルゴリズムは、冷静な分析よりも感情的な反応や拡散力を優先し、背景説明は後回しにされがちです。その結果、センセーショナルな話題だけでなく、教育・医療・環境・文化といった重要な分野においても、断片的な情報が誤解や偏見を助長する温床となってしまうのです。
さらに深刻なのは、「コメント」が「報道」に先行するという現象です。専門的知見や一次情報に基づく分析よりも、個人の感想や推測が先に可視化され、言説空間は感情的で断定的な言葉に満たされていきます。こうした環境では、事実の検証よりも「印象の形成」が優先され、たとえ後に訂正がなされたとしても、初期のイメージが記憶に深く刻まれてしまうのです。
そして忘れてはならないのが、「時間の非対称性」という構造的な問題です。司法・学術・行政といった制度的プロセスは、慎重な検討と時間を要します。しかし、SNSの情報循環は極めて短期的で、制度的な応答が間に合わないまま世論が形成され、政策や人事にまで影響を及ぼす事例が後を絶ちません。
今、私たちに求められているのは、単なる情報リテラシーの向上ではありません。それ以上に必要なのは、公共空間における「知の倫理」の再構築です。報道とは何か。共有とは何か。そして「知ること」の責任とは何か──。SNS型報道が日常となったこの時代に、私たちはこれらの問いを、改めて真剣に考え直さなければならないのです。
![[運営元名称]](https://nicapress.stglcts.net/wp/wp-content/themes/nicapress/assets/img/logo.png?20250704)